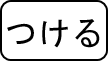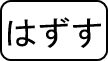第18回教育フォーラムの報告
11月3日(土)に第18回教育フォーラムを開催しました。今回のテーマは
「あなたも『開かれた学校作り協議会』のメンバーになれる!?~学校と地域が協力して子どもの学び・育ちを支える環境を目指して~」
ということで、来年度から全校展開する学校運営協議会機能を有した開かれた学校づくり協議会について、参加者の皆様と深めていきました。当日は、市内教職員、保護者、地域関係者、発表者などを含めて90名の方にご参加いただきました。以下、概要を報告します。
<第1部> 事業説明・実践紹介
(1)事業説明
・開かれた学校づくり協議会は「子どもの学び・育ち」を支えるため多様性・継続性をもって活動している。(平成13年度から設置)
・令和5年度4月から「学校運営協議会機能」を有する「開かれた学校づくり協議会」モデル校設置。令和7年度より全校展開(年4回程度→8回程度、8名以内→校長含む12名以内)
・学校運営協議会機能とは
→校長が作成する学校運営の基本方針の承認
→学校運営に関する意見を教育委員会または校長に述べる
→教職員任用に関する意見を教育委員会に述べる
(2)モデル校の取組について
○境南小学校開かれた学校づくり協議会委員より
・保護者以外はなかなか学校に関わりにくい。地域施設が協力できるんじゃないかと思い参加した。
・毎回の熟議で色々な立場で話し合うことが面白い。熱い話もあり、地域の絆づくりにもつながっている。
・世の中が複雑化し、色々な立場の意見を考える、集合知というのは社会的に大事になってくる。開かれた学校づくり協議会は、よいきっかけになっている。
・学校ごとの違いを比べてみたり、こうした取組を他の学校にも伝えたりしていきたい。
○第一中学校開かれた学校づくり協議会委員より
・武蔵野市との関わりがこれまでもてなかったが、今回、委員になることできっかけをもてた。不安だったが、実際に委員会に参加してみると、オープンで話しやすく、フラットな関係だと感じた。
・月1回の参加でどれだけ貢献できているか分からないが、部活動支援や職業講話などに関わることで、少しでも貢献できているのかなと思う。
・外部の委員がこうした開かれた学校づくり協議会に参加することで、学校に貢献できる、役に立ったというのは個人のモチベーションとしても高まる。
<第2部> パネルディスカッション「『開かれた学校づくり協議会』で学校は開かれるのか」
○:主な発言 ●:参加者からの質問や意見 →:質問等に対するパネラーの考え
○小学校は、機能強化した開かれた学校づくり協議会を進めるにあたり、子どもたちに「行きたい学校ってどんな学校?」と聞いたところ、「先生たちにも聞いた方がいいんじゃないか」となった。そのうえで、地域でできることを洗い出していった。その成果として、地域のお手伝いができる人リストを作ることができた。今後、その輪を大きくしていくことが課題だと思っている。
○中学校も同じように、学校のためにできることを先生方に意見を聞いた。14名の返信があったが、あまり期待をしていないようで、ショックだった。そこから、職員室に入り、先生方との受け答えや目に見える形で仕事をする中で信頼を得ようと考えた。部活動、給食、朝読書など先生たちの大変さを聞き、手伝えることを考えた。部活動や漢字検定や英語検定など手伝えることを行ってきた。
その際、ボランティアを募ったが、40名の方がその都度手伝ってくれる。ただ、実際平日の夕方に参加できる方は少ないので、地域の方に協力してもらう、謝礼など対価を用意できたらいいと思う。
○様々な会議に出る中で、地域とは誰のことを指しているのかがイメージできない部分があるのではないか。保護者の視点からも地域と言われてイメージができてないのではないか。その点、学校のお手伝いができる人などのボランティアを登録するというのはいい。
○地域はあくまでコンセプトだ。その地域に住んでいなくても、応援したいと協力している人は地域の人といえるのではないか。
○地域ボランティアのリストを広げていくのはいいが、信頼性をどうやって担保するのかが大切だ。
○学校の立場としては、学校のことをこれだけ一生懸命考えくださる方がいるということが嬉しい。学校のことを教職員だけでなく、地域の方が考えてくれていること自体が成果だと思う。
○PTAに関わることで、人の広がりができた。青少協など同時に近所に住んでいる年配の方なども大事にしていかなくてはならない。
○委員の多様性を担保することが大切だ。人は似たもの同士がどうしてもやりやすい。多様な人を意識的に入れることで、色々な子がいる現在の学校の状況を打破していける。
○全部の人を自分で集めるのではなく、一人が知っている人を一人、二人紹介するだけで、広がりが生まれる。委員を終えた人も応援団として関わってもらうといい。
<参加者からの質問・意見>
●開かれた学校づくり協議会に参画する仕組み、傍聴の仕方とかありますか。
→境南小学校では、学校だよりやメールなどで傍聴の機会を設けている。第一中学校も開かれた学校づくり協議会通信などで案内している。
→学校だよりは子どもが持って帰らない…。校支援メールは着実に届くようになっていいのではないか。
教育委員会からもっとお誘いするといいのではないか。
→強い関心がある人だけでなく、無作為に呼びかけて網を大きくするというのはあると思う。コストも考えて、色々組み合わせてやるといいかもしれない。
●情報の発信源として、地域掲示板、ムーバスの掲示板なども使うとよい。
●開かれた学校づくり協議会のゴールは何だろうか。
→毎年ゴールを決めるのは難しいが、委員が熟議の中で小ゴールを積み重ねることが大切ではないか。
→第一中学校は「地域と生徒をつなげる」ということを1年間のテーマにしている。
○開かれた学校づくり協議会の時間としては1時間30分~2時間くらいが妥当か。
○他で行われる熟議は3時間で完結までもっていくが、開かれた学校づくり協議会の場合、参加する人の都合を考えると1回で終わらせず、短時間の積み重ねが大切ではないか。
○開かれた学校づくり協議会を楽しそうに語られているのが印象的だった。第一前提として、学校が疲弊しているという状況を知ってもらうことだった。その上で、どうしていこうか?と応援団を考えていくことだった。
○現在は、立ち上げの時期だから頑張れるというのはある。全校展開や今後継続するには楽しさが大切。様々な楽しい関わりをしながら学校の応援団をつくっていけるとよい。
<参加者の意見の一部>
○今までの開かれた学校づくり協議会は、参画する仕組みや傍聴、議事録公開など普通の保護者や地域住民には全く開かれていないと感じていましたので来年度からどのように変わるのか楽しみです。
○当事者意識を持てる方が増えていくことが大事なのだと思います。
○まず、武蔵野市がこういうことをやっていることを今回初めて知りました。疲弊した学校の応援になりたいけどどうすればいいのかわからないなど保護者も思っています。当事者意識をみんなが持つためにもメンバーを代えていく、フィードバックをする必要があると思います。
○学校と地域が協力して子どもの学び・育ちを支えるということは、地域が学校を支えるという一方向ではなく、学校が子どもたちのために動いている地域(コミセンや子育て支援団体など)を支えるという双方向性があって回っていくのではないか。
○来年度以降も、こんな風にいろんな学校の開かれの様子を聞き、自校の特色を生かしながらも、他校のいいものを取り入れていけるような形ができていくといいなと思いました。
○子どものために、学校の教員も開かれることに慣れ、開かれることをプラスに考えられるよう変わっていく必要があると感じている。地域や保護者とともに学校がより盛り上がっていくとよいと思いました。
○本校も学校公開に、開かれた学校づくり協議会をライブでやってみたいと思いました。保護者には、傍聴・参加という形で、呼びかけたいと思います。まずは、たくさんの方に知ってもらうことが大事であると思います。
更新日:2024年11月14日 10:16:15